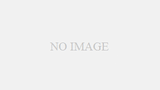ネット上の誹謗中傷や風評被害に対して「弁護士に削除を依頼しよう」と考える企業は少なくありません。しかし、弁護士に依頼すれば必ず削除されるわけではなく、手続きや費用、判断基準など、事前に知っておくべきポイントが数多く存在します。この記事では、削除依頼を弁護士に相談する前に企業が押さえておくべき重要な注意点を、わかりやすくまとめて解説します。
投稿内容によっては削除できないケースもある
ネット上の誹謗中傷や風評被害に悩んでいる企業にとって、「弁護士に頼めば削除してもらえる」というイメージを持っている方も少なくありません。しかし実際には、すべての投稿が削除の対象になるわけではなく、投稿内容によっては法的に削除が難しいケースも存在します。
削除が認められるかどうかの判断基準となるのは、主に以下の3点です:
- 投稿内容が虚偽かどうか(真実性)
- 公共性・公益性があるかどうか(社会的利益)
- 社会的評価を著しく下げる内容かどうか(名誉毀損の成立要件)
たとえば「〇〇の商品は期待外れだった」「接客が冷たく感じた」といった主観的な意見や感想は、表現の自由の範囲内とされることが多く、削除請求が通らないことがあります。一方、「〇〇は詐欺会社だ」「違法営業している」といった事実無根の断定表現は、名誉毀損や信用毀損に該当し、削除や賠償請求の対象となり得ます。
また、書き込みが匿名だったとしても、内容が感情的であっても、「法的にどうか」が最も重要な判断軸です。弁護士は法律に則って動くため、たとえ企業側が“許せない”と思っても、法的な根拠がなければ対応できないこともあります。
したがって、依頼前に「削除が通りやすい投稿かどうか」を一度冷静に精査しておくことが重要です。必要であれば、弁護士の初回無料相談などを利用して、削除の可能性について見通しを立てておくと良いでしょう。
削除までにかかる期間と費用の目安を把握しておく
弁護士に削除依頼をしたからといって、即日で投稿が消えるわけではありません。実際の削除までには一定の時間と費用がかかるため、事前にその目安を理解しておくことが、誤解や焦りを防ぐ上で重要です。
削除までのスケジュールは、以下のような手順で進行します:
- 弁護士との契約・投稿内容の精査
- 対象となるサービスへの削除申請(任意交渉または法的通知)
- 削除対応(任意or仮処分の取得)
- 必要に応じてIP開示・発信者特定へと進行
任意で削除に応じてくれるケースでは、早ければ1〜2週間程度で対応が完了することもありますが、仮処分など法的手続きが必要になる場合は、1〜3ヶ月以上かかることも珍しくありません。
費用に関しては、依頼内容や弁護士事務所によって異なりますが、おおよそ以下が目安です:
- 任意の削除請求のみ:10〜30万円前後
- 仮処分手続きを含む場合:30〜80万円程度
- 発信者情報開示まで含む場合:50〜100万円超
加えて、案件の難易度や対応回数によって、成功報酬や追加費用がかかることもあります。事前に「削除だけか、開示までか」「どの手段を用いるのか」を明確にし、見積もりを提示してもらうことが重要です。
削除までの道のりは、スピードよりも確実性を重視したいところ。焦らず着実に、実行可能な範囲での対応を進めましょう。
弁護士選びで重要なのは“IT・ネット分野の実績”
「弁護士なら誰でも対応できる」と思いがちですが、実際にはIT・ネット誹謗中傷に精通している弁護士を選ぶことが非常に重要です。一般的な民事・刑事を扱う弁護士と、ネット風評の実務に強い弁護士とでは、スピード感・精度・成功率に大きな差が出ることがあります。
特に、以下のようなポイントをチェックして選定するのが望ましいです:
- ネット誹謗中傷・風評対策の対応実績があるか
- ITリテラシーが高く、掲示板・SNS・検索エンジンに詳しいか
- スピード感を持って対応してくれる体制があるか
- 明確な費用体系を提示してくれるか
ネット誹謗中傷の問題はスピードが命です。投稿者のIPアドレスなどのログは数ヶ月で削除されてしまうため、対応が遅れれば遅れるほど特定が困難になります。したがって、「ITや掲示板の知識がある」「手続きに慣れていて、迅速に動ける」弁護士に依頼することで、より高い確率で問題解決につながります。
また、企業側としても「何が困っていて、どうなりたいのか」を明確に伝えられるよう、社内で対応方針や投稿一覧などを整理しておくことが、相談時の質を高めます。専門性と実績を見極め、信頼できるパートナーと連携することが、誹謗中傷対策の成功のカギを握ります。
自社対応と弁護士対応をうまく使い分ける判断軸
全ての誹謗中傷対応を弁護士に依頼する必要があるわけではありません。投稿内容や拡散状況、企業の体制によっては、自社で対応可能な範囲も存在します。だからこそ、「自社対応で済むもの」と「弁護士対応が必要なもの」の線引きをすることが、コストパフォーマンスの観点でも重要です。
たとえば、以下のようなケースは自社でも対応が可能です:
- 軽度のクチコミやレビューへの返信
- サービス改善・謝罪による収束が見込める投稿
- SNSでのユーザーとのやりとり(ただし慎重に)
一方で、以下のようなケースは弁護士への相談が推奨されます:
- 投稿が明らかに虚偽・悪意を含む場合
- 法人名や個人名を出した名誉毀損的内容
- 投稿が複数メディアに転載され、拡散している場合
- 投稿者の特定や損害賠償を検討している場合
また、法律的な手段が難しいグレーな投稿については、ネット風評対策会社との連携も視野に入れ、自社の広報力やリソースに応じて戦略を立てていくのが得策です。
弁護士に頼るべきタイミングを見極めつつ、自社の役割を理解しておくことで、過不足ない対応が可能になります。大切なのは「全部任せる」のではなく、「状況ごとに最適な選択肢を取れる」ことです。
まとめ
ネット誹謗中傷に対する削除対応は、弁護士に依頼することで法的に強力な手段を取ることが可能になりますが、事前に内容や条件をしっかり理解しておくことが重要です。すべての投稿が削除できるわけではなく、費用や期間も想定以上にかかるケースもあります。だからこそ、IT分野に精通した弁護士を選び、企業としての対応範囲も整理しながら、最も効果的かつ効率的な対応戦略を構築していく必要があります。準備と判断力こそが、被害の最小化と信頼回復への近道となるのです。